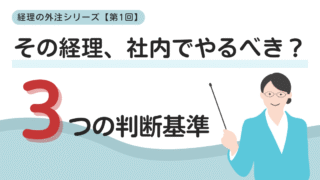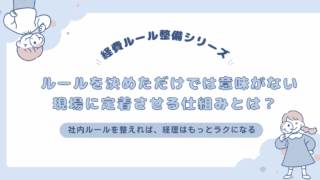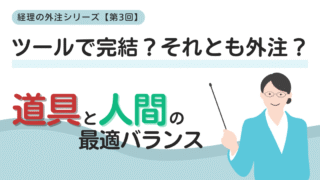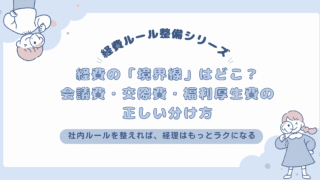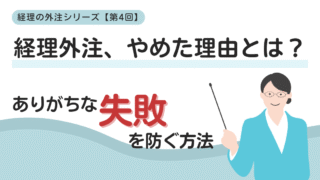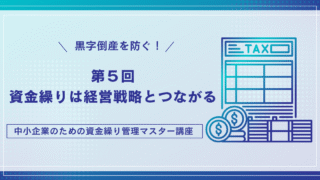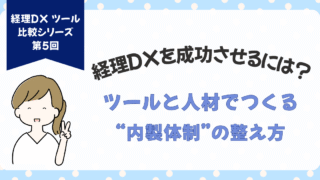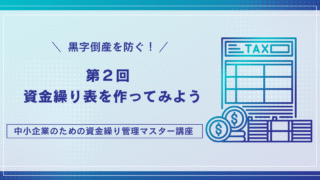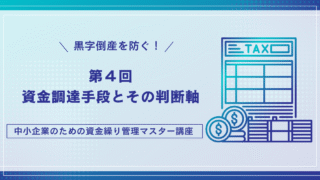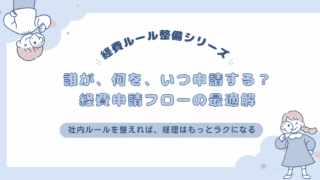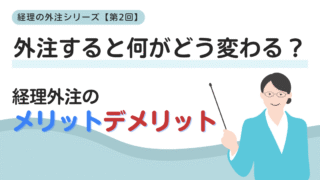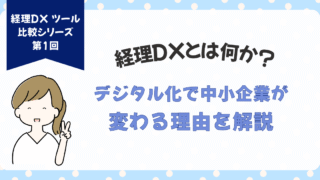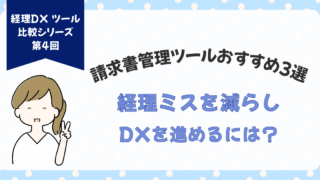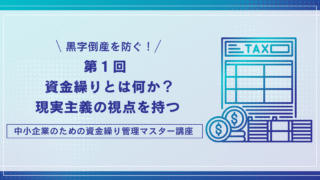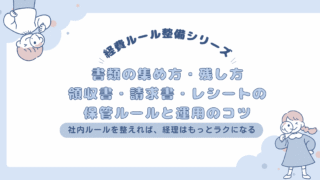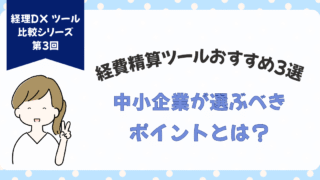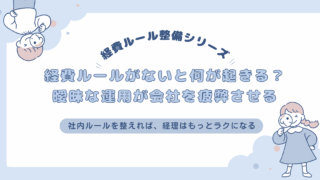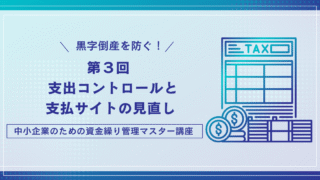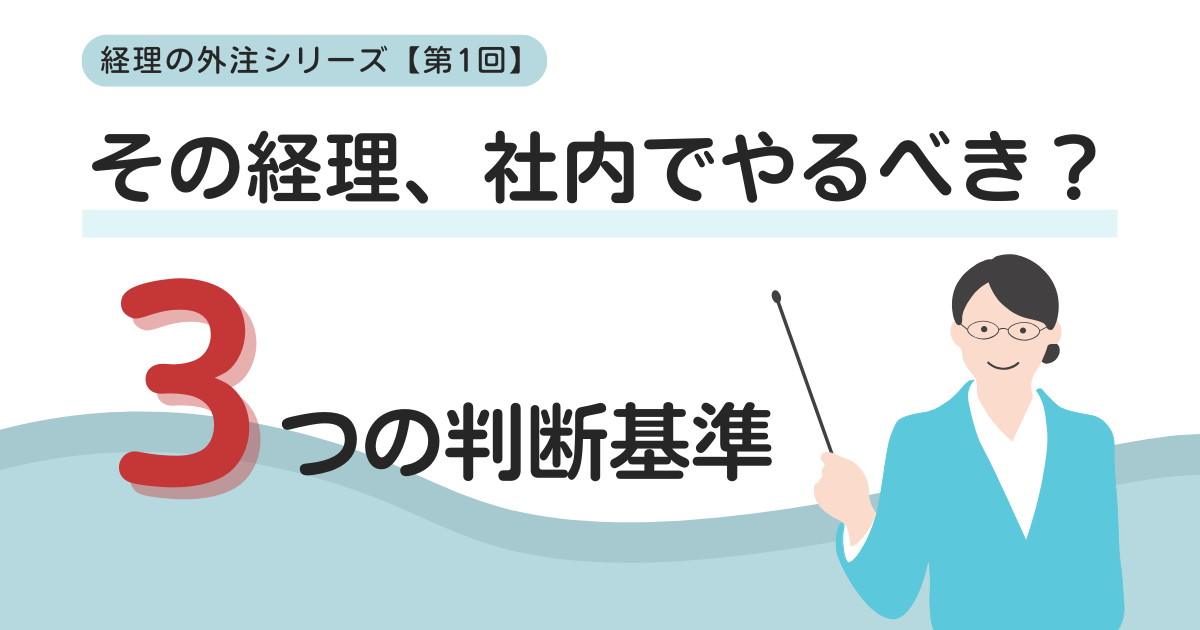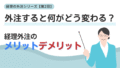「経理は社内ですべきか、外注すべきか」「どのタイミングで判断すべき?」
人材不足や属人化への対策、税理士との役割の線引きなど…そんな悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか。
本記事では「経理を外注すべきかどうか」を見極めるための判断基準を3つに分けて解説します。自社にとって最適な選択をするためのヒントをお届けします。
経理を”外注すべきか”の判断、悩むのは当然です
中小企業では、経理担当者が一人しかいない、あるいは他の業務と兼任しているケースが一般的です。そのため、業務量が増えたり、産休・育休などの長期休暇や決算期は、人手が足りなくなると考えられ、属人化や退職リスクも問題視されています。
そこで、注目されているのが経理業務の外注です。事業者やサービスによりますが、経理全般を委託することや、毎日の業務だけ、月次業務や年次業務だけを委託するなど様々な形があります。
しかし、安易に外注すると、日々の数字の動きが見えづらくなり、経営判断に影響が出るリスクもあります。
外注は便利な手段ですが、「丸投げ」ではなく自社にとっての適切な役割分担を考えることが重要です。
判断基準①経理担当の状況(人材と引き継ぎ体制)
経理業務を社内で担っている場合、「一人しか担当者がいない」「後任を育成できていない」といった状況は、リスクの高いサインです。担当者の急な退職や病気によって、業務が完全に止まってしまう可能性もあります。
このような属人化のリスクを減らす手段として「経理業務の外注」は便利です。特定の人に依存しない体制を構築できるため、安定した業務運用が期待できます。
一方で、外注に頼りすぎると社内で経理の知識が浅くなり、柔軟性が失われる懸念も。
外注を補助的に活用し、最終的な判断や経営に必要な数字の把握は社内で行う仕組み作りが理想です。
判断基準②業務の種類と範囲(経理全体or一部)
経営業務は多くあり、その全てを内製化・外注化のどちらか一方に決めるのは非現実的です。
主な業務を分類してみましょう。
経理業務の外注・内製の判断軸
| 経理業務 | 内容の概要 | 外注向き? | 備考 |
|---|---|---|---|
| 記帳(仕訳入力) | 領収書や請求書をもとに会計ソフトへ入力 | ◎ | 特になし(ルール化できる) |
| 請求書発行 | 発行のタイミングや書式が決まっている | ◎ | 顧客ごとの個別対応が必要な場合は注意 |
| 支払処理 | 毎月の定期的な振込処理 | ◎ | セキュリティ管理を要確認 |
| 給与計算 | 勤怠データをもとに算出 | ◎ | 給与体系が複雑な場合は注意 |
| 決算対応 | 決算書作成・税理士との連携 | ◎ | 高度な専門知識が必要なため |
| 売上集計・部門別損益 | 売上・原価を部門や商品別に分類 | △場合による | 自社の管理会計方針にそった対応が必要 |
| 資金繰り・資金管理 | 現預金の流れ・計画の可視化 | × | 経営判断に直結するため内製化が必要 |
| 管理会計(経営分析) | 利益構造 | × | 経営者の意思決定を支える情報源 |
種類を分けるポイント
・定型的でルール化できる業務(記帳、支払処理、給与計算など)は外注しやすい
・判断や調整が必要な業務(管理会計、資金繰りなど)は社内に残すのが原則
・特に「数字の意味を読み取る力」が必要なところは、経営と近い距離に置く
・業務を”全部まとめて外注”するのではなく、業務ごとに分解・設計することが重要
・細かい作業は外注できても、経営判断に直結する作業は内製化が必要
判断基準③経営者が数字をどう扱いたいか
経理の外注を考えるうえで、実は経営者自身のスタンスも大きな判断材料となります。
経営者のスタンスによって、経理の内製と外注は以下のように分かれます。
数字を”見て判断したい”タイプ
・会計ソフト(マネーフォワードなど)の導入をし自社で運用。
部門別、商品別などでデータを細かく管理していく。
・社内で月一回数字を見ながら「なぜ利益が下がったのか?どこが問題か?」を分析・議論する。
📍数字を「自分でみるため」にスピード・可視化を重視する
数字はよくわからないから”外に任せたい”タイプ
・記帳・請求書発行・支払処理・給与計算・決算対応は外注、資金繰り・資金管理、経営分析は社内で行う。
・税理士や経営コンサルタントなどと定期的に連絡をとりサポートしてもらう。
📍「基本は外注するけど、全ておまかせにしない」ことがカギ
経理は、単なる「お金の出入りを記録する人」ではなく、「共に管理していく存在」として機能させるべきです。だからこそ、数字の動きを自社で把握できる仕組みを持つことが、経理の安全性につながります。
まとめ「全部外注or全部内製」ではなく、”設計する”発想を
経理業務は、「全部外注」「全部内製」といった極端な選択ではなく、自社の実績に合わせて”設計”することが重要です。
まずは経営業務を細かく「分解」して、それぞれの業務が定型的なのか、判断が必要なのか見極めましょう。
そして、会社の成長フェーズに応じて、そのバランスを柔軟に見直し続けることが大切です。
今後のシリーズ記事では、経理業務を外注する際の注意点や、内製で進める場合の体制づくりなど、さらに実践的な内容を解説していきます。自社にとって最適な経理の形を、一緒に考えていきましょう。