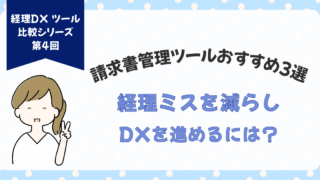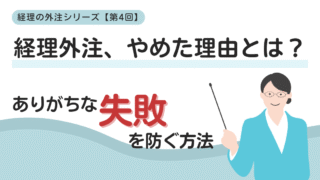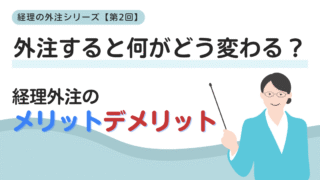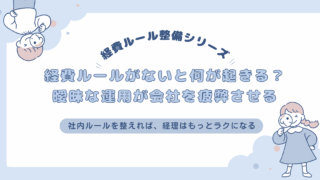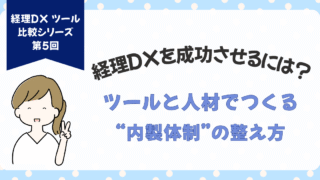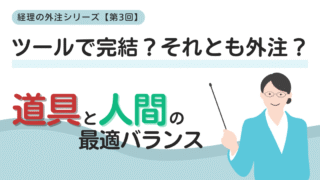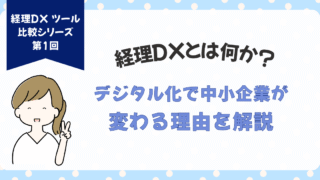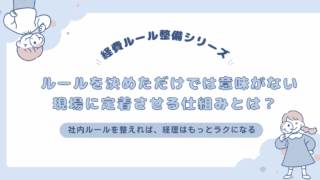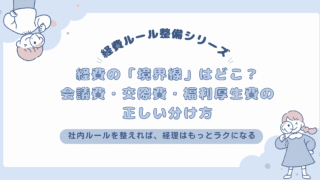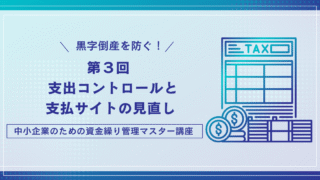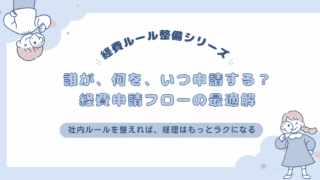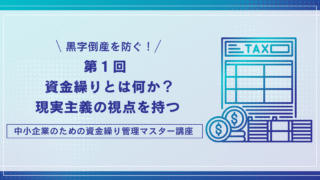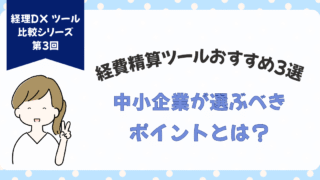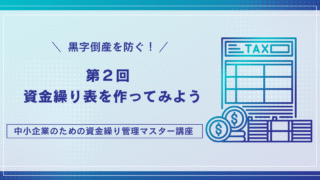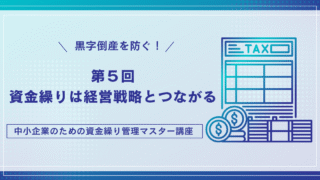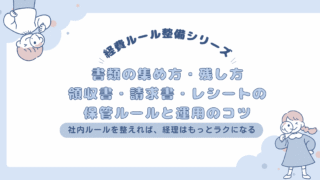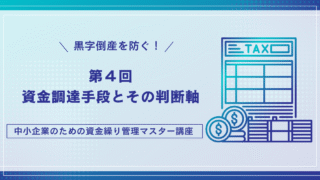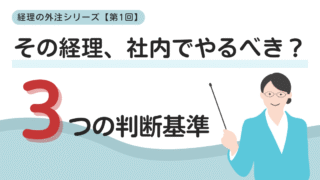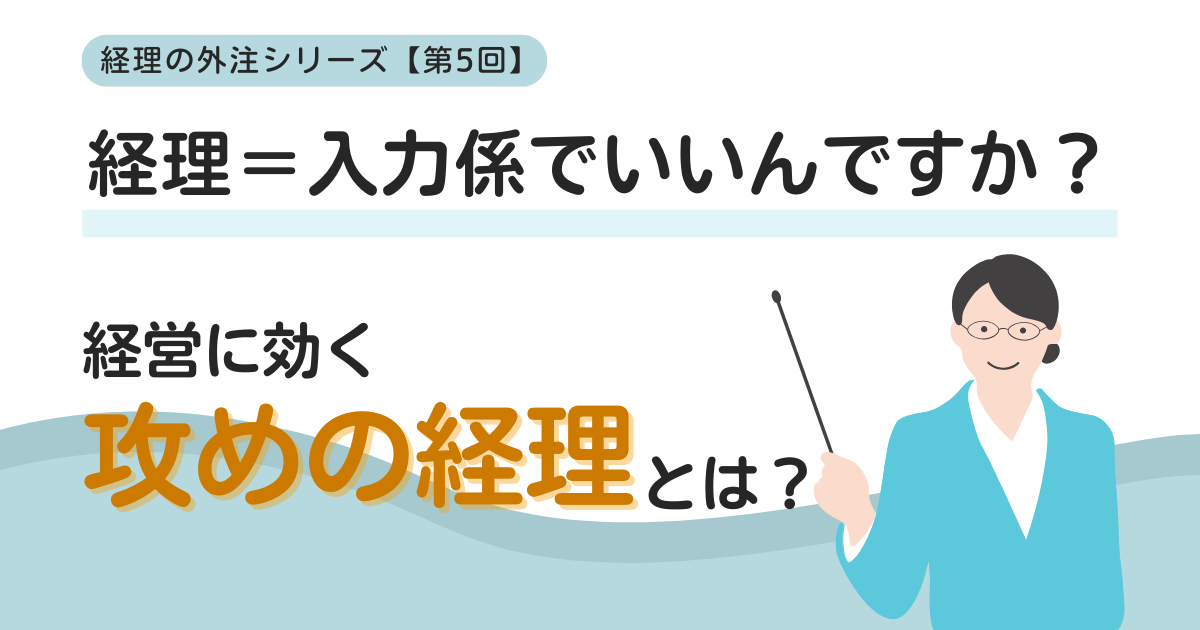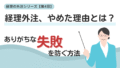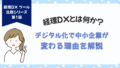第四回の記事では、経理の外注でありがちな失敗を紹介しました。
かつては「手間がかかるから外注する」が当たり前だった経理業務。しかし今、あえてそれを”内製化”する企業が増えています。背景には、スピーディな意思決定と、数字に基づいた経営力強化の必要性があります。
本記事では、経理内製化の進め方や得られる効果、そしてその背景にある経営意識の変化について詳しく解説します。
♦️なぜ経理を内製化する企業が増えているのか?
経理判断に必要な「数字」がすぐに見えない課題
外注先に経理を任せていると、「月末の締めを持たないと数字が出てこない」
「今すぐ欲しい分析データが手に入らない」といった不便さが生じます。
スピード重視の経営判断には、リアルタイムで”数字が見える”環境が求められています。
| 外注経理と内製経理との違い(スピード面) | ||
|---|---|---|
| 項目 | 外注経理 | 内製経理 |
| 月次締めの完了タイミング | 外注先のスケジュール次第 | 自社都合で調整可能 |
| 急な数値分析への対応 | 即時対応は難しい | 社内で即分析できる |
| 経営会議への準備時間 | 外注先に依頼が必要 | 自社で柔軟に作成可能 |
「攻めの経理」への移行を目指す企業が増加
いま、経理には単なる記帳や精算だけではなく、”経営に貢献する部分”としての役割が求められています。
管理会計や予算実績の管理(予実管理)、KPI分析(組織やプロジェクトの目標達成に向けた進捗状況を数値で評価するための指標)など、戦略的な意志決定を支える経理への進化が求められているのです。
📝必要となる経理スキル例(攻めの経理)
・管理会計の設計力
・予実管理レポートの作成
・KPIを数値化・分析する力
・経営者との対話力
社内に数字を読める人を育てたいというニーズ
経理を内製化することで「経営の数字に強い社員」を社内に育てることができます。これは単なる業務スキルの育成ではなく、”自社の未来を絵が描く力”を社内に残すことにもつながります。
💡外注任せの落とし穴
経理をすべて外注していると、決算書や試算表が「ただの報告資料」として届くだけになりがち。
それでは、”なぜ利益がでたのか” / ”出なかったのか”を分析し、改善につながる力は育ちません。
♦️内製化のステップ | 失敗しないための過程
現状の業務棚卸しと外注範囲の明確化
まずは取り組むべきは、「いま、何を外注しているか?」の可視化です。
記帳、支払い、請求管理、決算対応…業務ごとに内製と外注の境界を整理しましょう。
| 📄業務範囲の棚卸しシート(例) | ||
|---|---|---|
| 業務項目 | 外注 or 内製 | コメント |
| 請求書発行 | 内製 | 営業部が対応中 |
| 給与計算 | 内製 | 経理担当が対応 |
| 月次締め処理 | 外注 | 月末~翌月10日完了 |
| 記帳業務 | 外注 | 税理士に委託中 |
内製化に必要な人材・スキルの確認
内製化には人材確保が欠かせません。中小企業では「一人経理」が現実的な選択になるケースも多いため、必要なスキルを網羅できる体制設計が求められています。
👥内製化に必要なスキルセット
・経理実務(記帳、仕訳、振込)
・会計ツールの操作
・Excelなどによる分析資料作成
・経営視点
ツールとルールの整備
クラウド会計ソフトや管理会計ツールを導入し、業務の属人化を防ぐルールを整備しましょう。
| ⚒️整備しておきたい主なツールと仕組み | |
|---|---|
| ツール例 | 用途 |
| クラウド会計ソフト | 中小企業向け・記帳・振込・経理精算 |
| オンラインバンク | 自動振込 |
| スプレッドシート | KPI・予実の管理表作成 |
| 経理マニュアル(PDF) | 仕訳・締め処理の手順 |
移行期間を設け、段階的に進める
一気に内製化するのではなく、段階的なハイブリッド運用が成功のカギです。
まずは月次処理から→支払業務→決算補助…という順で進めるとスムーズです。
📆移行ステップの例
ステップ1:月次の試算表作成だけを内製化(初月~3か月)
ステップ2:支払業務も内製化(4~6か月)
ステップ3:決算補助も一部対応(7か月目以降)
♦️経理を内製化することで得られる3つの効果
スピードと柔軟性の向上
社内でリアルタイムに数字が見られるようになり、経営判断のスピードが格段にアップします。
社員のスキルと意識が育つ
数字への感度が上がり、経営者と現場の対話がスムーズに。
「数字が読める現場担当者」は、組織全体の武器になります。
経営の精度が高まる
利益率、部門別の収支、顧客ごとの採算性などを定期的にチェックでき、”なんとなくの経営”から脱却できます。
✅まとめ | 経理を取り戻すことは、会社の力を取り戻すこと
経理の内製化は、「コスト削減のため」ではなく「会社の経営力を底上げするため」に行うものです。
全てを自社で抱え込む必要はありませんが、「数字で経営する力」を社内に持つことが今後ますます重要になります。
📣シリーズ最終回のご案内
これまで全5回でお届けした「経理外注・内製シリーズ」
自社にあった体制設計のご相談も承っています。興味のある方は、お気軽にご連絡にご連絡ください。