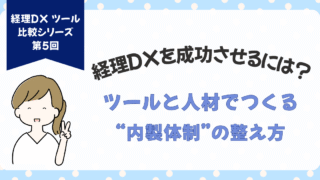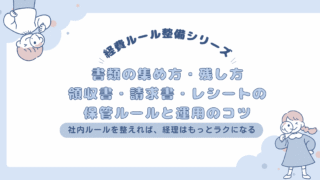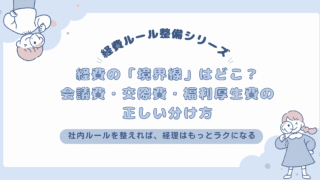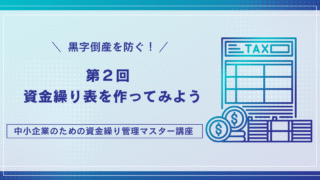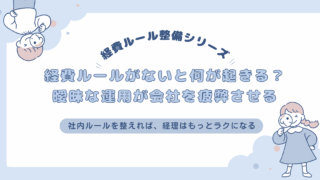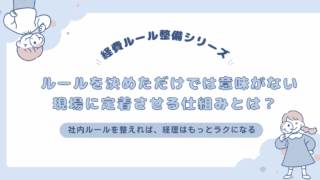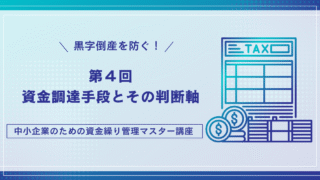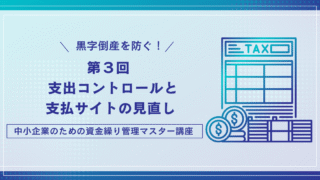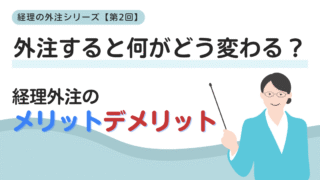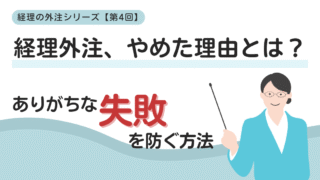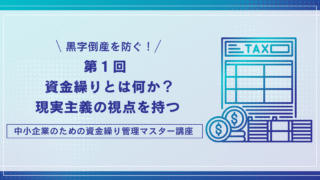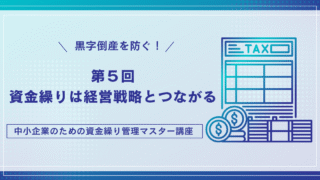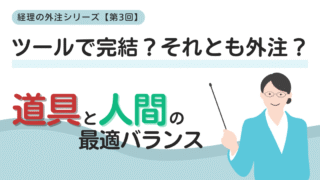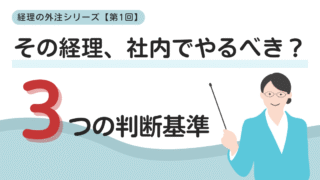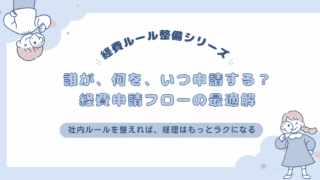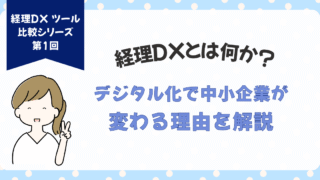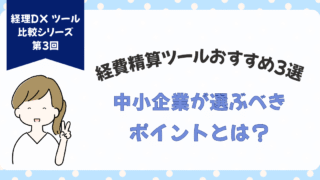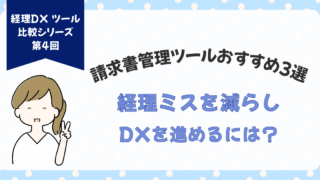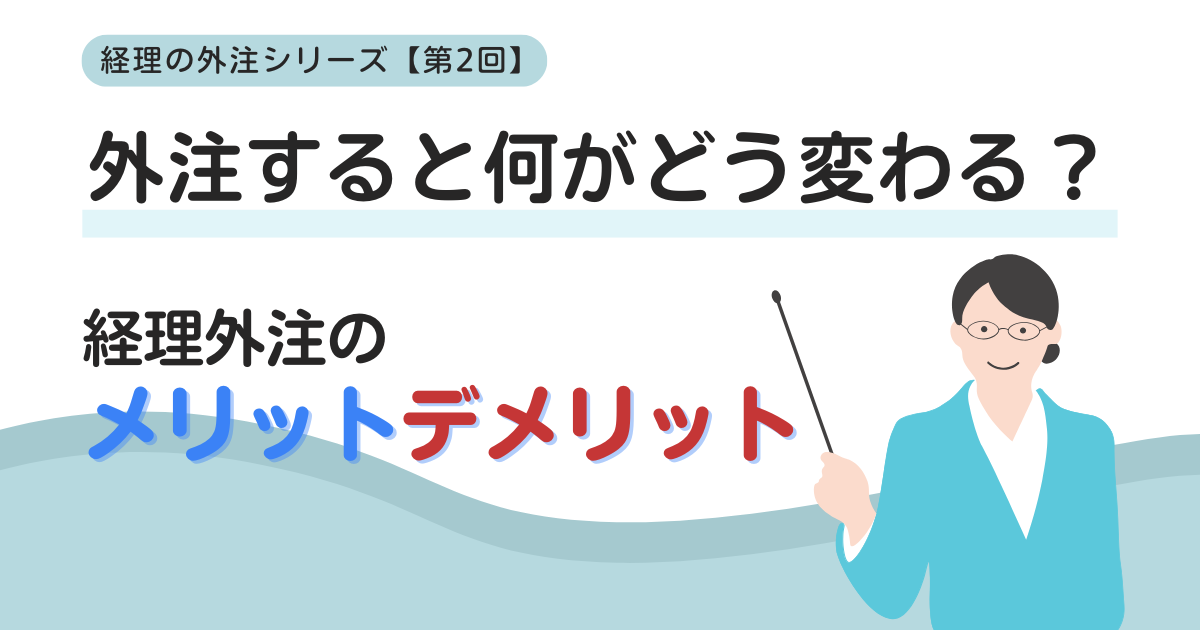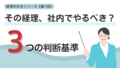第一回目の記事では、経理の外注を判断するポイントをお教えしました。
外注は、「専門家に任せられて安心」「業務が楽になる」といった印象から、導入を検討する中小企業が増えています。しかし、全ての企業にとって最適とは限りません。
本記事では、経理を外注するうえでのメリット・デメリットを整理し解説します。
経理を外注するメリットとは?
経理を外注することで得られるメリットは多岐にわたります。以下に主なポイントをまとめました。
1️⃣専門性の高い対応が得られる
・専門知識の活用
会計士・税理士などの専門家が対応し、正確な処理が期待できる
・法改正への対応力
税制改正や会計基準の変更にも即応できる体制が整っている
・ミスの防止
プロによるチェック体制があるため、仕訳ミスや漏れが減少する
🔍経理専門の知識や経験が社内にない企業でも、プロのノウハウを活用できます!
2️⃣属人化リスクを軽減できる
・担当者の退職対策
社員に依存せず、外部のチームが対応するため急な退職の影響を受けにくい
・業務の可視化
業務フローが整理され、外部の知識を活かした運用が可能
・業務の安定化
業務プロセスが標準化されることで、継続的で安定した対応ができる
🔍経理が一人に集中している中小企業では、業務停止のリスクを抑えられるのが大きな利点です!
3️⃣コア業務に集中できる
・経営資源の集中
経理業務に費やす時間・労力を減らし、本業や経営判断に集中できる
・作業の効率化
外注することで社内の作業時間が短縮され、生産性の向上が見込める
・戦略的活動の強化
財務分析や資金調達など、より戦略的な経営に時間を振り分けやすくなる
🔍特に人手の少ない中小企業にとっては、業務負担を軽減し、事業成長に集中できる大きな効果があります!
経理を外注するデメリット・リスクとは?
外注には多くの利点がありますが、以下のようなリスクも無視できません。慎重に判断するために、主なデメリットをまとめてみました。
1️⃣タイムラグ・意思疎通の問題
・タイムロスの発生
データのやり取りに時間がかかり、リアルタイムでの対応が難しいことがある
・緊急時の対応の遅れ
「今すぐこの情報が見たい」といった要望に外注先が即対応できないケースも
・コミュニケーション課題
業務内容を伝えるのに時間がかかり、スピードが落ちてしまう
‼️注意点‼️
迅速な経営判断を求められる場面では、”外注のスピード感”に不満を感じることも…
2️⃣会社の数字が”見えなくなる”
・報告の理解不足
経理の知識が社内にないと、外注先の説明が理解できず、経営者の判断が鈍る可能性がある
・数字への感度の低下
社内の経理に関与しない分、数字への意識が薄れがちに
・経営のブラックボックス化
数字の裏側を把握できず、業績悪化に気づくのが遅れるリスクも
‼️注意点‼️
経理を「外に出す」ことで、会社のお金の流れが”自分ごと”でなくなる危険も…
3️⃣外注先の質や依存度によって差がでる
・スキル差
対応者の経験や対応力に大きなばらつきがあり、サービスの質に差がでやすい
・外注先への依存
業務をすべてを任せすぎると、外注先にトラブルがあった際に業務が止まる恐れあり
・コスト優先の落とし穴
価格だけで選ぶと、対応力が不十分でかえってコスト増や手戻りになるケースも
‼️注意点‼️
信頼できるパートナー選びが成功のカギ!安さだけで判断するのはNG❌
外注を検討するべき前に確認すべき3つの視点
外注を検討する際には、以下の視点を事前にチェックすることが重要です。
☑️現在の経理業務の整理度
(例)手順やルールが整っているのか?誰が何をしているか明確か?
☑️社内の「数字を見る」文化
(例)月次の報告を見て経営判断しているか?数値の変化に敏感か?
☑️外注範囲の見直し
(例)記帳や支払業務だけを外注し、請求管理などは、社内で続けるという”部分外注”も検討可能
✏️アドバイス
いきなり全部を任せず、”外注できる部分”から段階的にスタートするのがおススメです!
まとめ 「手放すこと」が目的化していないかを見直す
経理の外注は業務効率化を高める有力な選択肢ですが、「とにかく楽をしたい」だけでは失敗のもと。目的を明確にし、体制を整えたうえで進めることが成功のカギです。
・外注は手段である
→「経理をなくす」のではなく、「数字を活かす」ために外注を活用する
・体制整備が重要
→数字を読み、意思決定に使う体制が社内にないと、外注の価値を活かしきれない
・部分外注の活用
→段階的に任せる範囲を広げていくことで、無理なく安定したアウトソーシングが実現が可能
📚第3回では「経理業務をどう”切り分けるべきか?”部分外注の比較」を詳しく解説❗