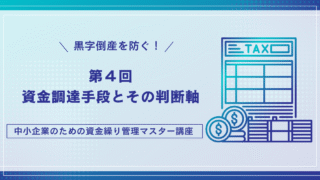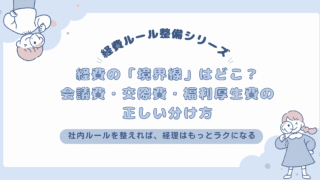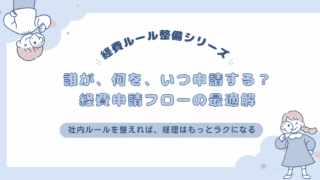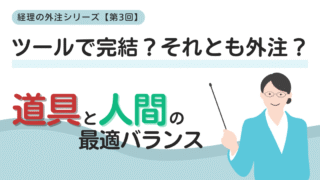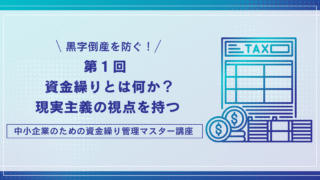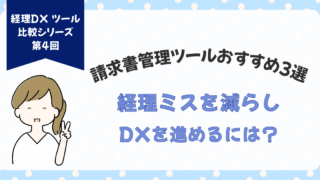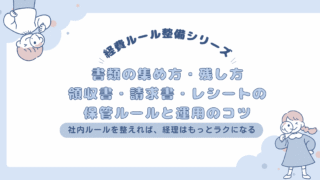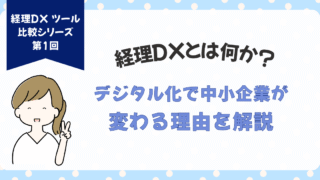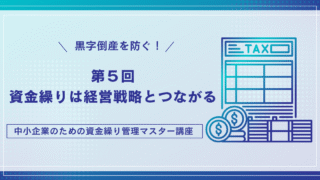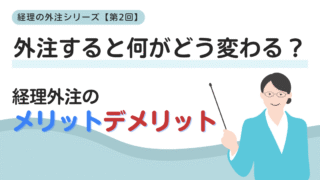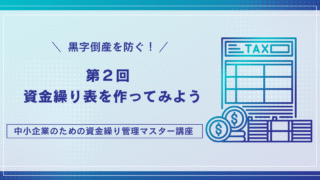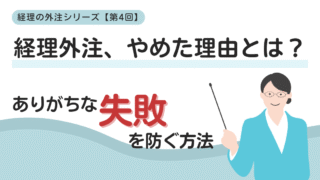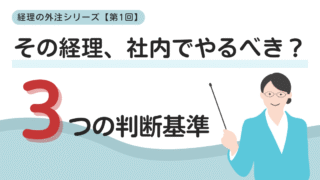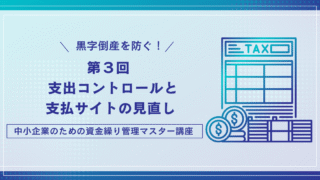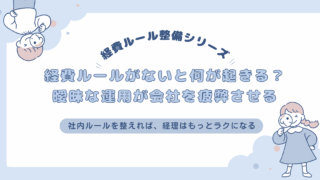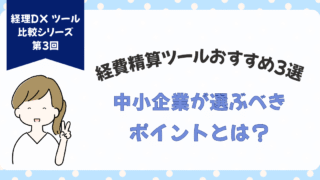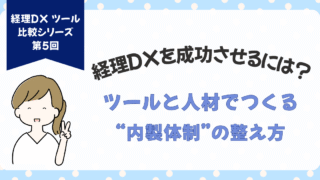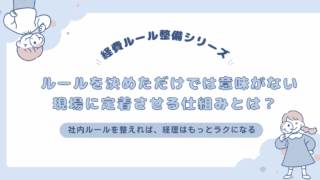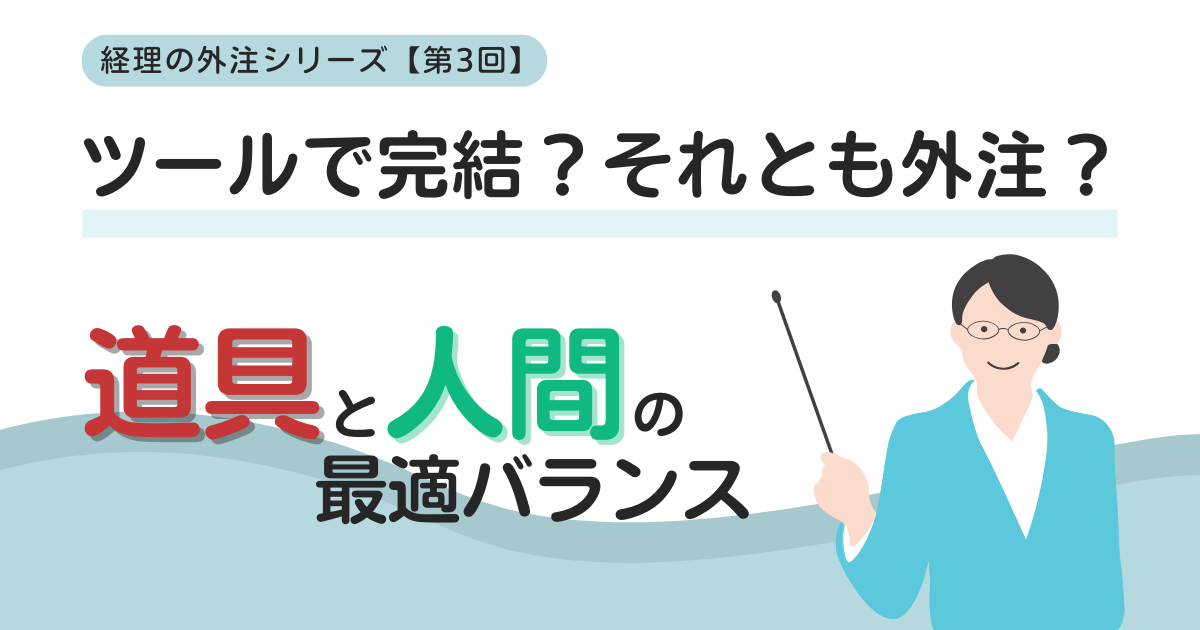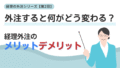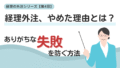第二回の記事では、外注するメリット・デメリットをお教えしました。
経理業務を外注すれば効率化できると思っても、「すべてを外に出す」ことは現実的ではないケースが多くあります。では、どこまで外注すべきで、どこからは社内で担うべきか?
その判断は、業務の性質や会社の体制によって変わります。
本記事では、中小企業が経理業務を上手に切り分けるための視点と、外注しやすい業務・内製すべき業務の具体例を解説します。
経理業務は「全部」か「ゼロ」かではない
経理には様々な業務が含まれており、それぞれに「外注向き」「内製向き」があります。
一括して考えるのではなく、業務単位で判断することが成功のポイントです。
| 経理業務の主な分類と特徴 | ||
|---|---|---|
| 業務内容 | 特徴 | 外注との相性 |
| 記帳(仕切入力) | 定型・ルール化しやすい | ◎ |
| 請求書の発行 | 顧客との関係性・タイミングが重要 | ◎ |
| 支払処理 | 要承認・タイミングが重要 | ◎ |
| 給与計算 | 勤怠データをもとに作成 | ◎ |
| 月次試算表・帳票作成 | 数字の解釈が必要 | × |
| 資金繰り・予実管理 | 経営判断と密接 | × |
💡ポイント
細かく切り分けることで、「ムリなく・ムダなく」外注が活用できます!
外注しやすい経理業務とは?
外注に向いているのは、ルーティン業務で、標準化・マニュアル化しやすいものです。
記帳代行・領収書整理
相性の良さ:★★★★★
・業務の特徴
領収書・請求書の元に会計ソフトへ仕訳入力を行う
・外注のメリット
業務を丸ごと任せられ、社内の負担を大きく減らせる
・注意点
証憑の整理・提出方法をルール化しておく必要がある
・活用ツール
会計ソフトを活用
給与計算・年末調整
相性の良さ:★★★★★
・業務の特徴
給与・手当・控除の計算、社会保険・源泉徴収などを含む
・外注メリット
法改正対応・計算ミス防止が期待できる
・注意点
社員情報・評価との連動が必要なため、信頼できる外注先を選ぶ必要がある
支払処理(振込・ネットバンキング)
相性の良さ:★★★★★
・業務の特徴
支払予定表の作成、振込データの登録、承認フローの整備が必要
・外注メリット
承認権限や手順を明確にすれば、実行部分だけを委託することが可能
・補足
銀行のシステム(API)や会計ソフトなどを組み合わせると、手作業による時間と手間を削減できとても効果的
内製すべき経理業務とは?
外注が難しいのは、判断や社内理解が必要な業務です。単に数字を出すわけではなく、その意味を理解し、意思決定に反映させる力が求められる部分は、内製化をおすすめします。
月次の収支確認・管理会計の読み解き
・試算表などの数値を見て、「なぜ増減したか」「来月はどうするべきか」を考えるのは社内の役目
・外注先は”数字を作る”ことはできても、”読み解く”ことはできない
資金繰り・予算策定
・資金繰りの調整、借入タイミングの判断などは経営に直結
・「経営者の考え」や「今後の戦略」まで把握していなければ対応できない
社内への経理教育や業務改善
・業務の見直しや社員教育は、社内に知識を残す必要あり
・外注だけでは社内文化が育たず、属人化や非効率化を改善できない可能性も
経理業務の”切り分け”をするための実践ステップ
外注の可否を判断するには、まず現状を見える化し、業務を客観的に分析することが重要です。
ステップ①現在の経理業務を洗い出す
・担当者ごとに「何を」「どこまで」やっているか一覧にする
・属人化している部分が明確になる
ステップ②業務ごとに評価
☑️定型性
業務の手順が誰にでも同じように対応できるか?特別な判断や例外対応が頻繁に発生していないか?
☑️重要性
経営判断に直結する?
☑️頻度
毎日?毎月?年に一度?業務量の安定性は?
ステップ③「外注」「内製」「ツール自動化」で振り分け
(例)
| 分類 | 業務例 | 特徴 |
| 内製 | 資金繰り、予算策定、経営分析 | 戦略や判断に直結、外注に向かない |
| 外注 | 記帳、給与計算、年末調整、振込データ作成 | 定型業務、ルール化しやすい、ボリュームがある |
| ツールで自動化 | 領収書の取り込み、支払通知の作成など | クラウド会計ソフトや銀行とのシステム連携で効率化可能 |
ステップ④定期的に見直す
・年に一回程度、経理業務の見直しを実施
・組織体制や業務量の変化に応じて、外注範囲を柔軟に調整する
まとめ”全部外注”はもったいない。賢く分けて効率と経営力を両立
経理業務は、単なる「数字の処理」にとどまらず、経営判断を支える土台でもあります。
すべてを外注すれば楽になるかもしれませんが、それでは会社に「数字の感覚」や「現場の温度感」が残りません。反対に、なんでも内製化して抱え込むと、リソース不足に陥りやすく、ミスや非効率の温床になります。
🔷経理は「処理」だけではなく「経理のための数字づくり」も担う
・日々の仕訳や月次処理は、最終的に「経理の判断材料」になる
・数字の裏にある”意味”を社内で考えられる体制が不可欠
🔷外注は使い方次第。やりすぎも、やらなすぎも非効率
外注のしすぎの例
1.数字の解釈まで任せようとして失敗
→外注先が整えた数字の意味を社内で読み取れず判断を誤る
→数字を見る文化が育たない
外注のしなさすぎの例
1レシートの記帳まで全て任せる
→経理担当者が処理に追われる
2.属人化し、担当者が抜けると業務の停止
→内製に偏りすぎていると、業務ノウハウが属人的になり、引き継ぎが困難
リソースが十分な企業では、内製も有力な選択肢。ただし、人手が足りない状態で”全部内製”にこだわると、かえって非効率になることも…
外注と内製の役割を明確にし、「任せるべき部分」を見極めることが重要です。
💡バランスの取れた切り分けが、最大のパフォーマンスをうむカギです。
📚第4回では、外注の失敗から学ぶべきポイントを紹介❗
実際の企業でよくある「経理外注の失敗例」を次回記事でご紹介します。
・なぜその外注はうまくいかなかったのか?
・どこで判断を誤ったのか?
・成功している企業との違いとは?
「経理外注」を”効率化”ではなく”経営強化”につなげるために、必見の内容です!!